アーヴィングほか
「未亡人の一年」(上)
「未亡人の一年」(下) ジョン・アーヴィング著
アーヴィングのなにがすきなのかというと、この人の作品の根本で脈々と流れるユーモアだ。
これはかなり初期の作品からそうだったのだが、このアーヴィングという人はどんなに悲惨な物語を書いても、それがただの暗い話という風にはならないのだ。
それどころか、悲劇的な事件の中に垣間見出来る、小さな小さな吹き出し笑いのような瞬間をいくつも盛り込んでは、読者の麻痺した感覚に訴えかけてくる。
この作品においても、母親が二人の息子を事故で失ってしまい、「失った息子達を取り戻すために」もう一人子供を作っては見たものの、生まれてみたら女の子だったこともあって、子供を全然愛することが出来ないという最悪な設定である。
とは言え、そんな悲しみのどん底といったような状況においてもまた、アーヴィングの笑いのセンスは休まることがない。
例えば、母親が夏休みにアルバイトで家にやってきた16歳の男の子と関係を持ってしまい、夏の間に60回セックスすることになるのだが、その男の子が長じて作家になった後、その60回のことばかり書くということなど、はっきり言って面白すぎる。
その上、その男の子は自分が中年になった後も、その母親のことが忘れられずに、自分よりも年上の女性にばかり魅力を感じるというのも、痛ましさをはるかに超えたおかしさがある。
だって40代後半の男が80代の女性とつきあっちゃったりするのだ。
こういうことを真剣に書けるのは、はっきり言ってアーヴィングだけではあるまいか。
そして忘れてはならない、物語の牽引力。
小説家なので当然、時には失敗作を書くこともあるのだが、作品としての失敗、成功は別としても、やはりその作品を最後まで読ませる力量には脱帽してしまう。
しかし、アーヴィングという人は、ナチュラルな状態である種の女性に好かれてしまって仕方ないという男性を書くのが本当にうまい。
つい先日読んだ「第四の手」でもそうだった。
しかもその人は、手が片方ないのに、それすらなんら障害になる気配がなかったもんなあ。

- 作者: ジョンアーヴィング,John Irving,都甲幸治,中川千帆
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 2005/08
- メディア: 文庫
- 購入: 2人 クリック: 28回
- この商品を含むブログ (38件) を見る

- 作者: ジョンアーヴィング,John Irving,都甲幸治,中川千帆
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 2005/08
- メディア: 文庫
- 購入: 1人 クリック: 6回
- この商品を含むブログ (25件) を見る
-
- -
「アニマル・ロジック」 山田詠美著
黒人女性ヤスミンの血に住んでいる「なにか(後に“ブラッド”という名がつく)」が見た、ヤスミンとその周辺の人々のラブ・ライフとそれ以外の生活。
ヤスミンが黒人であることにより、人種差別のエピソードが続々と出てくるのだが、主人公であるヤスミンはそんなことには目もくれない。
彼女は他人との個人的な結びつきにおいても、稀有というほかないほどさっぱりとした観念の持ち主で、嫉妬やら束縛というような感情からは完全に逸脱している。
つまり、これ以上ないほど「自由」な人間なのだ。誤解を恐れずに言うと、これは女性としては殆ど奇跡的な特質である。
そして、この彼女の持ち合わせる自由奔放さは、彼女が黒人であることとはまったく関係なく、むしろ、その美貌や性格に大きく結びつく類のものである。
最初のうちは、この「なにか」の視点から描かれる物語に違和感を覚えて仕方なかったが、読み進めるうちに段々と慣れた。
でもなんていうか、そこに必然性みたいなものはあまり感じない。
だって、この血液中を流れる存在ですらも、最終的にはかなり人間的な観念を持ち合わせていくことになるのだ。
こういうのって、リダンダンじゃないだろうか。
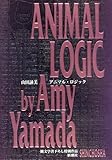
- 作者: 山田詠美
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1996/04
- メディア: 単行本
- クリック: 4回
- この商品を含むブログ (8件) を見る
-
- -
「卵一個分のお祝い。−東京日記」 川上弘美著

- 作者: 川上弘美,門馬則雄
- 出版社/メーカー: 平凡社
- 発売日: 2005/09/01
- メディア: 単行本
- 購入: 2人 クリック: 23回
- この商品を含むブログ (153件) を見る